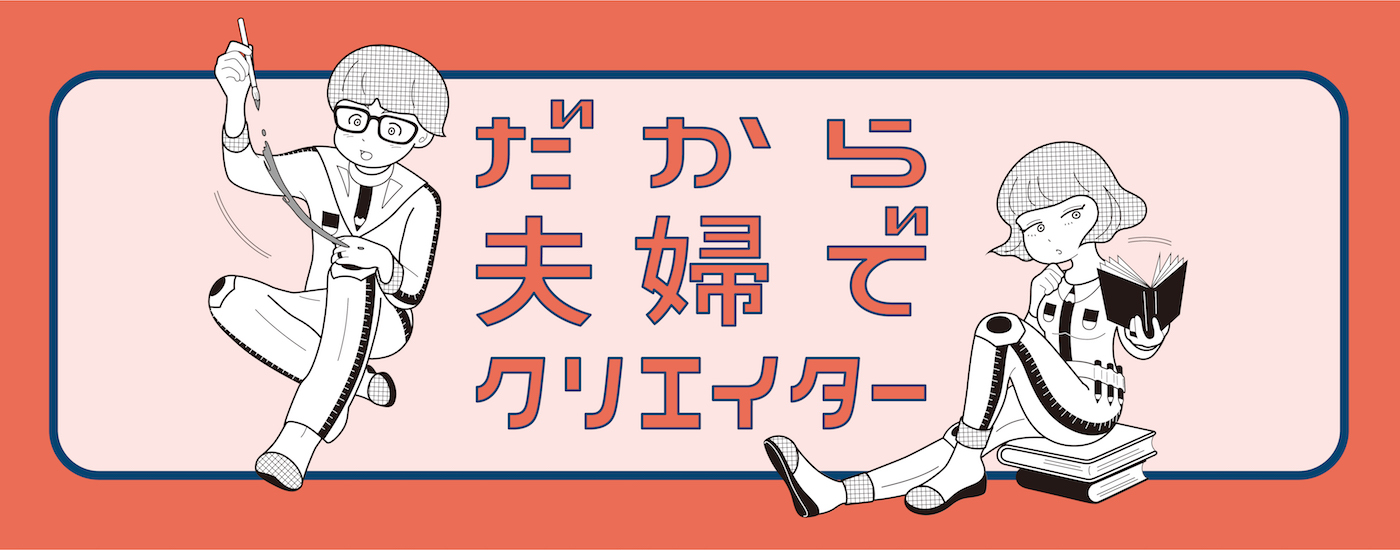連載「だから、夫婦でクリエイター。」の第二回に登場するのは、神奈川県三浦市三崎で唯一の出版社を営むアタシ社のミネシンゴさんと三根かよこさん。ふたりはこれまで、それぞれに編集長となって雑誌を刊行したり、ブックフェアを開催したりと精力的に活動している。そして、2017年12月に活動拠点を逗子から現在地に移すと、事務所の1階に蔵書室「本と屯」をオープン。出版社、本、読者がより密接な関係になれる場所を生み出した。そんなふたり、じつは意外にファンキーな一面も。出版社をマグロ漁船に見立て、本で一発当てたいと話す。そんなことを話していたら「だから、夫婦でクリエイター。」のわけが見えてきた。
夫婦で出版社を営む理由、そして可能性
ーー編集者とデザイナーの夫婦ってけっこう多いと思うんですけれど、出版社を営んでいるのは珍しいですよね。
かよこさん:個人事業主として受託案件を中心に回すのではなく、版元になって自分たちが興味のあるものを制作していく方がエキサイティングな気がしたんです。前職では広告制作を中心に仕事をしていたんですけれど、それを続けることへのしんどさを感じることがけっこうあったので。
シンゴさん:ふたりともそういうタイプなんですよ。自分たちの表現を追求したい。自分がいいと思うものをつくって食べていきたいっていう。そうすると、版元になってしまうのがいちばんてっとり早いんですよね。あとはお互いにギャンブラー気質なところがあるので。ちょっと極端な言い方だし、合っているかわかりませんが、マグロ漁船に乗っている感覚。
かよこさん:うん。小さくまとまるのではなく、虎視眈々と大物を狙いたい(笑)。
シンゴさん:ホームランを打てるかもしれない土俵があるのなら、そっちの方がいいじゃんって思うんですよ。会社で働いていると、決められた分の稼ぎにしかならないじゃないですか。でも、例えば1500円の本を出して、それが仮に1万部売れたら1年は食べていけると思うんです。もちろん、それ以上になる可能性もあるし。そこがWeb媒体との大きな違いでもあって。広告収入は別として、仮に10万PV稼いだとしても1円にもならないじゃないですか。

ーーとはいえ、出版社という形態になることで在庫を抱えるリスクなども発生しますよね。それについてはどのように考えているんですか?
かよこさん:私たちが定期的に刊行している『髪とアタシ』と『たたみかた』については、どれくらいの部数が売れるのか? 精緻に見立てを立てられるので、在庫を大量に抱えるリスクはあまり考えてなくて。
シンゴさん:あと雑誌って、普通は委託販売で定価の12~13%の利益を書店さんが得るのが基本なんですけれど、僕たちのところは買い切りにしてもらっていて。でも、その分、書店さんの取り分を30%~40%に設定しています。そうすると、書店さんとしても売る目的ができるじゃないですか。利益率が高いから。だから、いい場所に置いてくれる。そうやって出版社と書店が徒党を組んで一定の数を売っていかなきゃいけないと思うんですよね。その母数をどれだけ増やすことができるか。
かよこさん:そのうえで、まずは必要な部数を刷っていくようにしているんです。それでどんどん刷り増ししていく。最近は経験値も上がったから、これくらいの部数は売れるだろうっていう見込みで強気にいくこともあるんですけれど。でも、最初の3年くらいは飛び込み営業をせっせとやっていました。
シンゴさん:いやいや、君は一度も営業してないじゃん(笑)。
かよこさん:まあ、それは役割分担ということで。

ーーそれでいうと、雑誌のつくり方についても、ふたりだからこそできる方法なのかなと思うのですが、そのあたりについてはどのように考えていますか?
シンゴさん:自分の化身みたいな感覚はありますよね。ミュージシャンとか落語家とか、美容師もそうですが、自分の腕一本で表現して飯を食べている人たちにすごく憧れています。そういうことを自分は雑誌をつくることでやりたくて。真っ向から言えない気持ちを間接的に伝えていきたいというか。
かよこさん:だから、大手出版社の企画会議では絶対に通らないようなことばかりテーマにしていると言われることもあって。ふたりでやっているから、売れるか売れないかを度外視でつくることもできるんです。
ーーそれは大手ではなかなかできないことですよね。
かよこさん:単純に、大手とうちみたいな小さな出版社では、役割が違うのかなって。“ふたりだからできる”って、言い換えれば“ふたりの範疇でしかできない”とも言えるし。すごく私的なものをつくりつつ、商業的に売れることを目指しているので。私たちがおもしろい観点や切り口を持ち続けなければ、たちまち売れなくなっていくと思うんですよ。そこに対する危機感みたいなものは常にあって。結局、生き様がそのまんま本になるので、成長と変化を日々繰り返していくしかないんですよ。いろんな人に会って、いろんなことを試してって。
逗子市から三浦市三崎へ。それによって変化したふたりの意識
ーー逗子市から三浦市の三崎に引っ越してきて変わったことはありますか?
シンゴさん:いちばん大きな変化は「本と屯」ができたことですね。僕たちふたりが持っていた本をすべて置いているんですけれど、見ず知らずの人が来るようになって、仕事以外のコミュニケーションが増えました。本屋なのか、休憩所なのかよくわからない空間。でもそこに必ず「人」がいて、なにかしらのコミュニケーションが生まれています。
ーー『note』にも「子どもが来て本を読んでくれる」みたいなことを書かれていましたよね。そういう出来事って未来に繋がる話なのかなと思ったりするのですが、実感はありますか?
シンゴさん:“人は読みたい本があれば読む”ということが少しだけわかった気がします。ここには、僕たちふたりが子どものときに読んでいた絵本とかも置いてあるんですけれど、同年代くらいのお母さんがそれを見つけて子どもに読み聞かせすることもあって。しかも、本を売ってほしいと頼まれることもあるんですよ。蔵書だから基本的に販売はしてないんですけれど。今って書店だけじゃなく、ネットでも気軽に本が買えるじゃないですか。そういう流れの中ですごく前時代的というか、逆行するような形で売買が成立することがある意味で新鮮だなと。
かよこさん:日本のどこにいても、Webで本をポチれるようになったから、本を買うという行為に差をつけられるとしたら“誰から買うか”だと思うんですよ。三崎に引っ越す少し前に『10代の自分へ。逗子ブックフェア』というイベントを主催したんですけれど、そのときの来場者が200人弱、本が400冊も売れて。それって大型書店の1日の売り上げに相当するらしいんですけれど、そういうことの延長線上に「本と屯」はある気がしますね。
ーーアタシ社が蔵書室を運営することの必然性もそこに繋がりますよね。
かよこさん:出版社が本との接点をつくるのはすごく大切なことなんですよ。ふらっと立ち寄ってくれた人たちが、アタシ社の本を買ってくれたりするので。
シンゴさん:それに最近は、蔵書室をやることが三浦市にとっても重要だと感じています。こういうインタビューを読んで遊びに来る人とかもけっこういるし、本を寄贈したいという人も現れたりするんです。三崎の人に「寄贈したいから運ぶの手伝って」と言われたり、扉の前に紙袋が置いてあって、そこに手紙と本が入っていたり。予想外のことが多々起きています。


ーー三崎に引っ越してきてからフェーズが変わってきた印象はあるんですか?
シンゴさん:逗子市のときもそうだったんですけれど、三浦市にも出版社がないんですよね。これだけ世の中にさまざまな業種・職種があるのに、出版社って意外と少ない。というか、東京に集中しているだけだと思うんですけれど。だからこそ、僕たちにできることがあるのかなって。
ーーというと?
シンゴさん:逗子市で創業してから2年ほどいたんですけれど、出版を通じて街にコミットすることってそんなにやっていなかったんですね。でも、三崎に来てからは、地域に根づいた仕事も増えていて。春先には三浦市の人々をテーマにした写真集を出版する予定です。ほかにも郷土資料をうまくアレンジして残せないかと考えていたり、三崎のフリーペーパーもつくりたいなって。三崎にある出版社だからこそ、できることを考えています。
かよこさん:需要と供給がマッチしたと思うんですよね。逗子市にいたときも取材を受けることはあったんですけれど、行政の方から引き合いはなかった。私たちも「逗子市のために何かやりたい」っていうマインドを持ってなくて。それはなぜかと聞かれるとよくわからないんですけど。でも、三崎に引っ越したことで変わりました。
シンゴさん:けっこうグッとくることが多いんですよね。例えば、引っ越してすぐ市長さんと話す機会があって。そこで「月に三浦市で何人亡くなられているか知ってる? 30人。でも、この街で30人も毎月生まれてると思う? 引っ越してきてると思う?」みたいな話をされて。そういうことを市民が認識しているし、事実として僕らの住んでる家の周辺もおじいちゃんやおばあちゃんしかいない。そういうものを見たり聞いたりしていると、勝手に使命感が生まれるというか。追い詰められると人は動く、ということを三崎に来てすごく感じます。




かよこさん:それで私たちも少しずつ街のために動きたいと思うようになったんです。最初はそんなつもりはなかったんですけれど(笑)。消滅可能性都市に指定されていると聞いたら、やっぱり何かできないかなって思うじゃないですか。
ーー市長と話す機会ってなかなかないですよね。
かよこさん:ここに引っ越してからすぐに来てくださいました。
シンゴさん:僕らの知らないところで出版社がきたぞって話が広まっていたのかなあ。
ーーローカルコミュニティの伝達力はすごいですね。
シンゴさん:みんなTwitterとかやってないんですけどね(笑)。ほんとに情報が回るのが早いんです。街が小さいから目立つみたいで。30代の子どもがいない夫婦で、さらに出版社をやっているから。
かよこさん:しかも、ちょうど私たちが引っ越してくるタイミングに『ユニバーサル広告社』という寂れたシャッター商店街を蘇らせるドラマを三崎で撮影していて、ドラマの主人公が住むことになる家が、この「本と屯」だったんです。そういう偶然が重なりあって。でも、最初は「街のために何をしてくれるの?」と期待されたとしても、困るなと思っていました。そういう目的のために出版社をやっているわけではないので。それに、なにかやるにしても対処療法みたいなことをしたくないんですよね。
シンゴさん:もともと三浦市って3軒しか新刊を販売している書店さんがなくて、そのうちの1軒が昨年末に閉店したんです。最近もTSUTAYAが閉店して。だから残り2軒しかない。これってけっこう危機的状況じゃないですか。そういう中で、僕たちが媒介になって街が盛り上がっていくと夢があるなって思うんですよね。前例があるかわからないんですけれど、版元と地域の書店が手を組んで売り上げをつくっていくとか。でも、それもできる気がしていて。

ーーどうしてそこまで三浦市や三崎にコミットするようになったんですか?
シンゴさん:ふたりとも田舎がないからですかね。僕は横浜市で、妻は千葉と東京なので。ローカルに移住する人が増えている中で、もうひとつ居場所をつくりたくなったんですよね。東京にそれをつくるのは難しいし、逗子市も街としては大きいから中途半端で。長野の方も検討していたんですけれど、東京から少し遠いし。だから三崎がちょうどいいんですよね。ギリギリ東京と繋がっていられる感じがします。
かよこさん:でも、三崎に住む人たちは、ここをローカルだとは思っていないんです。東京の人たちと話すと「ずいぶん不便なところに引っ越したね!」みたいなことを言われるんですけれど、私たちは「そうかな?」って。品川まで70分の距離を近いと思うか、遠いと思うか。その感覚の違いなのかなと思います。
分かり合えないことを前提にした距離の取り方
ーー今回こうやってふたりにインタビューする機会があり、少し印象が変わりました。特にかよこさんは、思ったよりもファンキーな人だなって(笑)。
かよこさん:よく言われるんですよ。思ったより身長がデカかったとか(笑)。
シンゴさん:かよこはSNSもあんまりやってない人だからね。でも、話すとおもしろいんですよ。
ーーおもしろいですね。ふたりの生活はすごく楽しそうです。仕事をしているときはどんな雰囲気なんですか?
シンゴさん:和やかではないよね。多分、人が思っている以上に丁寧な暮らしみたいなことはしてなくて。そういうことも嫌いではないんですけれど。
かよこさん:どちらかと言えば、爆笑と怒号が飛び交う感じ(笑)。やっぱり魂のぶつかり合いみたいなものがないと、いいものはできないから。
シンゴさん:多かれ少なかれ、夫婦で仕事している人たちはそうだと思いますよ。

ーーそれは具体的にどんなところであるんですか?
シンゴさん:このレイアウト全然違うみたいなことを言ったら、「は?」みたいな感じで返されたり。
かよこさん:それは丸投げ感があるからだよ。写真とテキストだけ送られてきても「これに思いは込められているのか」ってなるじゃん。「お前が編集者でいる意味はなんなんだよ」みたいな。そうすると「指示出すと怒るから」とか言い訳されるからそうなるの。
シンゴさん:こんなふうに夫婦だと遠慮がないから、普通の編集者とデザイナーにある「ちょっと違うんだけど、言いづらいしこのままいくか」みたいなこともなくて。とことん精度を高めていけるのはメリットかなと思います。
かよこさん:とはいえ、ふたりで仕事をしていても分かり合えないこととか、共有し合えない部分もあるんですよ。それはもう音楽性の違いみたいなもので。だけど、そこで変に仲良くするのではなく、分かり合えないことを前提に極限まで詰めていく感覚がいいのかなと思っています。
ーーふたりで企画会議とかはすることはあるんですか?
かよこさん:一切しないですね。
ーー「今すごい企画を思いついたんだけど、ちょっと聞いてよ」みたいなこともないですか?
かよこさん:そういうことで相談して「つまんない」とか言われると「お前に言わなきゃよかったわ!」となるので。特に、お互いが編集長をやっている雑誌については企画会議にアサインすらされません。
シンゴさん:でも、仕事の話は常にしてますね。それこそ、ご飯を食べるときはもちろん、寝る直前まで。
かよこさん:変にわかった気にならず、ときにくっついたり離れたりしながら歩んでいく。それくらいが私たちには心地いいのかなって。

PROFILE
アタシ社
神奈川県・三浦市唯一の出版社。ミネシンゴさんが編集者、三根かよこさんがデザイナーという最小単位の布陣で本づくりを行っている。美容文藝誌『髪とアタシ』、渋谷発のメンズヘアカルチャーマガジン『S.B.Y』、30代のための社会文芸誌『たたみかた』などを発行しているほか、事務所の1階で蔵書室「本と屯」を営んでいる。