編集者・長畑宏明さん(写真・右)が、インディペンデントマガジン『STUDY』を出版したのは2014年のことだった。それから約4年を経た2018年7月28日に5号目が全国の書店で発売となった。月刊誌であれば半年で達成する数字である。だが、それを選択しなかったのは、紙でしか表現できないことを追求していきたいという確固たる意志が長畑さんにあったからに違いない。
特にテン年代は雑誌不況を背景にした休刊・廃刊が相次いだ。が、それはある意味で自然淘汰と読み取ることもできる。その一方で、Web媒体も一時期にその数を急激に増やしたが、マネタイズやグロースなどの問題から終わりの道を選ぶケースも増えた。では、これからの時代に必要とされるメディアのあるべき姿とは一体どのようなものなのだろうか?
『STUDY』でアートディレクターを務める一ノ瀬雄太さん(同・中右)、そして長畑さんや一ノ瀬さんと旧知の仲であり、インディペンデントマガジン『skydiving magazine』の発行者でもある平野正子さん(同・中左)と村田実莉さん(同・左)を交えて考察してもらった。
Webではなく、紙というメディアを選ぶ理由
——最近の傾向として、感度の高い人ほどWebと距離を置いた形でメディアをつくっている気がするんですね。そういう意味では、みなさんは紙というフィジカルなものに価値を見出している当事者なのかなと。そこであらためてお伺いしたいのですが、どうしてアウトプットがWebではなく、紙だったのでしょうか?
長畑さん:単純にWebでやるよりもコストが安かったんですよ。結局300万とか400万くらいお金をかけて広がっていくものを比べると、圧倒的に紙の方が濃さも速さもあって。それは最初からなんとなく考えていたことでもあり、後から確信に至ったことでもあります。
一ノ瀬さん:僕は、単純に本をつくることが楽しいから。特に『STUDY』はバンドを組んでる感覚が強くて、なんというか仕上げていく喜びみたいなものがすごくあるんです。
長畑さん:僕と一ノ瀬くんにとって、紙は若い頃から慣れ親しんだものなんですよね。だから、メディアのフォーマットとしてはすごくスタンダードなものだし、デジタルと対極にあるものという考え方でもないから敵対意識もない。でも『skydiving magazine』の二人は、僕たちと世代が異なるので、そもそもの考え方が違うんじゃないかな。

(左)今年7月に発売された『STUDY』最新号。今号から雑誌コードを取得し、全国の書店で流通している。
(右)『skydivingmagazine』EPISODE3。表紙は見る角度によって、コムアイと会田誠が入れ替わる不思議な作り。
平野さん:『skydiving magazine』を発行したときに『SUPER PLAT』という展覧会を開催したんですが、そのときのコンセプト文でもちょっと述べていることがあって。簡単に説明すると、いまのWeb上にある情報って、人がこれまで本で残してきたものをアップロードしたものに過ぎないと思うんですよね。
長畑さん:アーカイブするっていう意味?
平野さん:そうです。本って損壊しやすいものではあるけれど、歴史的に残りやすいものでもあるなって。人間って昔から何かを記して残してきましたよね。石版を削ったり、インクで書いたり。それって文明の発展とも密接に関係していて。いまはWebに辿り着いてるんですけど、万能ではない気がするんです。HTMLが変わっちゃうと読めなかったりするし、サイト自体が消えることもあるから。でも、印刷したものって残るんですよね。

長畑さん:確かにアウトプットの形態は紙が安定してるよね。
一ノ瀬さん:「本は死んでも残る」ってよく言うんだけど、実際に神保町の古本屋さんに行くと、お婆ちゃんが生涯書き溜めてた詩を編纂して葬式で配った詩集とか売ってるわけ。めちゃくちゃ良いよね。
長畑さん:わかる。この前ソール・ライターっていう写真家の写真展に行ったんだけどさ、彼が晩年に撮りためていたものを息子さんが集めて編集したらしいんだよね。そういうことが起こるのもきちんと形として残っているからだし。
一ノ瀬さん:データはさ、消えちゃうから。僕の周りには映像クリエイターがけっこう多いんだけど、例えばCMなんて短くて1週間くらいしか放送されないしね。
長畑さん:その期間見逃したら終わりやもんな。たまたま何か観たい番組があって録画してたら入ってたみたいな。
一ノ瀬さん:だからこそ、いまでもみんなの記憶に残っている日清カップヌードルの「hungry?」とかはすごいんだけどさ。
長畑さん:でも、さっき言ってたアーカイブに残すという意味では、Webは便利だよね。アップロードしておけば検索して辿り着けるから。ただ、それでもWebだと機能しないなって思うことがふたつあって。ひとつはメディアが機能しない。それは連続性がないから。結局見出し文化になるんですよ。そうなると、単体の記事で情報量をできるだけクリアにして、いまの時代にある程度フィットさせたものをつくらなきゃいけない。だから、ファジーなものが伝えられなくなる。AだけどBだけど、Cでもないみたいな話はすごく伝えにくい。
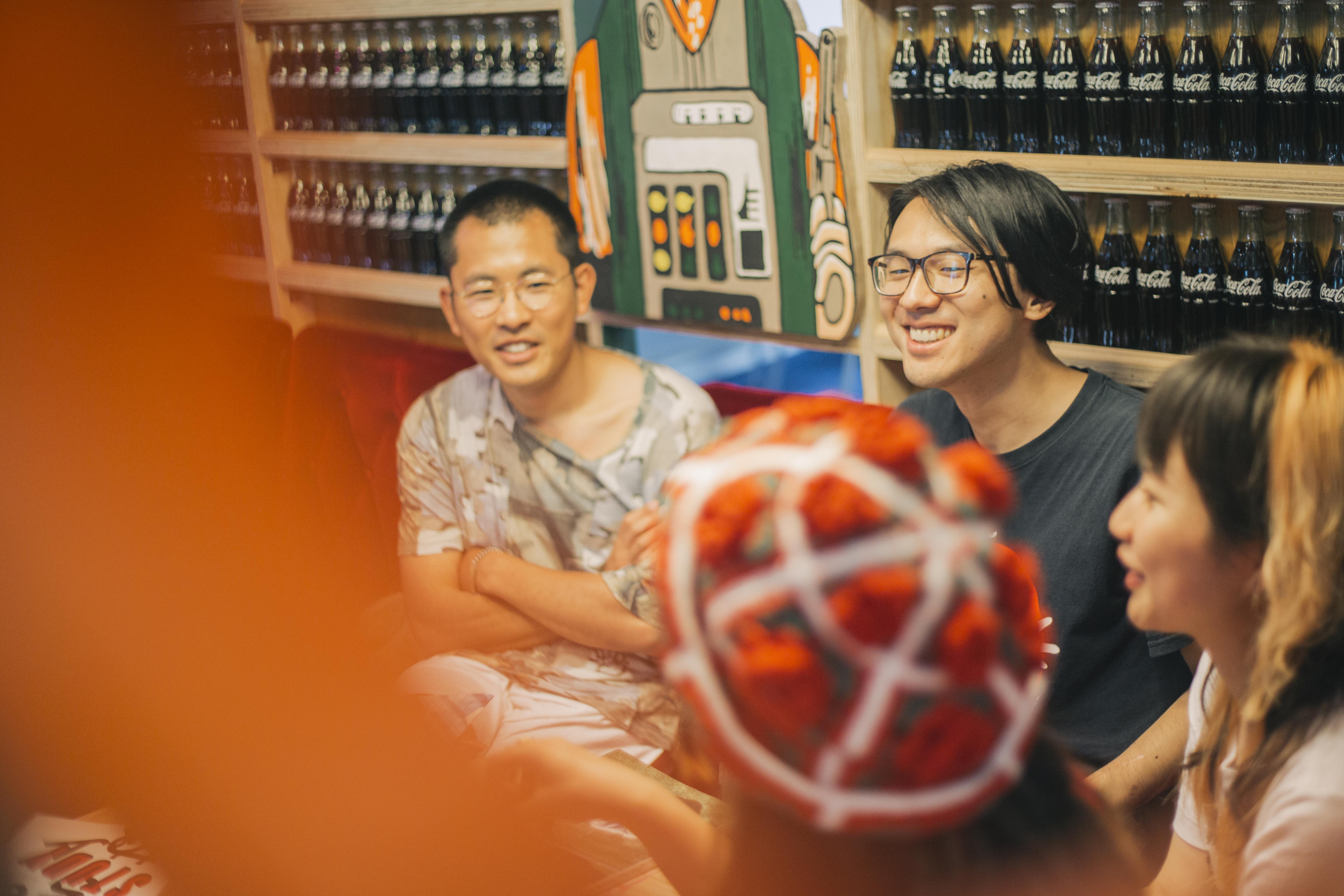
長畑さん:もうひとつはデザインがあんまり機能しないなって。これは一ノ瀬くんともよく話すんですけど、デザイナーにとって Webは自由度が低いし、アウトプットの機能性も感じられない。例えば、本だったらある1ページにすごく小さな画像を配置してそこに意味性を持たせたりできるんだけど、Webだと「ちっさ!」で終わりでしょ。
平野さん:うんうん。
長畑さん:あと、Webって人の好奇心の速度とそぐわない気がして。1週間とか数日にひとつ記事をあげるじゃないですか。でも、そんなに記事にしたいことってあるのかなって。どれだけ有名な人でも、本当にインタビューされるべきタイミングって一生に何回かだと思うんですよ。それがWebになると広告に紐づけて毎週アップされたりする。でも、実際はそこまでの需要はなくて。だからこそ、さっき言ってたWebはメディアとして機能しづらいっていう話にも繋がるんですけど。
——その意味では『STUDY』も『skydiving magazine』もじっくり時間をかけて制作していますよね。そういう時間のかけ方についてはどう考えていますか?
一ノ瀬さん:『skydiving magazine』って発行する頻度を決めてるの?
平野さん:年に2回はやりたいよねって話はしていて。今年の秋に一冊出す予定です。
長畑さん:これ、どれくらいの時期から考え出すの?
村田さん:前の号をつくっている途中から「次回はこういうのがやりたいよね」って話をして、それから二人で資料となるものを探していく感じですね。写真を撮って送るとか、こんな面白いことがあったって話をしたり。
平野さん:なぜか編集作業に追い込まれてるときに、次は絶対これじゃんとか言い出したりして。
村田さん:そうそう。「私も同じことを思ってた」とか言って。
長畑さん:そしたら、あんまりモチーフに困ることはないわけだ。二人はリズムが合ってるんだね。
一ノ瀬さん:『skydiving magazine』はすごく二人の人格が現れているメディアだよね。
長畑さん:うん。実物の二人とコントラストがなさすぎるよね。だからこそ、本当に好きで『skydiving magazine』を制作しているのが伝わってくる。
村田さん:褒められた(笑)。

一ノ瀬さん:今ってInstagramとかで話題を集めることもできるわけじゃん。でも、こうやって本をつくってるのはなんでなの?
村田さん:本が好きだったんですよね。
長畑さん:あ、やっぱり本は好きだったんだね。
平野さん:好きでしたね。
村田さん:でも、Webで展開することを考えてなかったから、今になってどうしようかなって思い始めてます。Instagramも更新しなきゃって(笑)。
一ノ瀬さん:あ、それは一緒!
長畑さん:うちらも早くデジタルに移行したくて仕方がないんだよね。
次号のアイデアが浮かぶ瞬間がいちばん面白い
——『skydiving magazine』は制作中に次の号のイメージ湧いてくるという話がありましたが、『STUDY』はどうですか?
長畑さん:一緒ですよ。もう早く次の号がつくりたい。なんだったら、次の号のアイデアを思いついたときが最高に楽しいですよね。
村田さん:それは本当に思う!
長畑さん:あと『STUDY』の場合は、制作中にできなかったこと、人から刺激を受けたことを次号のためにメモしておくようにしていて。それもなんだかんだ変わっちゃうんですけどね。真逆を行くこともあるし。

一ノ瀬さん:『skydiving magazine』を読んでると、本をつくるのが最終目的じゃないように見えるんだよね。これは二人にとってのInstagramでありTwitterでもあり、人格を理解するためのものじゃない? だから、すごく現代的というか、個人がメディアを持つことをうまく表現している気がする。
長畑さん:なんかヒップホップのアーティストみたいだよね。『skydiving magazine』がミックステープの役割を果たしていて、良いなと思った人がコンタクトを取ってきてくれるわけでしょ。その軽やかさが羨ましくもあるし、良いところなんだろうなと思います。
平野さん:そうですね。紙面ではコラボレーションが発生しないけど、この媒体を通じて知り合った人と一緒に何かできるのが面白いなって思います。だから、ミックステープって言われて本当にそうだなと思いました。
長畑さん:『skydiving magazine』があるから二人に頼みたいって気持ちになるよね。
——『skydiving magazine』を制作する際に意識していることはありますか?
村田さん:みんなに受け入れてもらえるものをつくることがすべてだとは考えてなくて、むしろ「なんだ、これ?」っていう違和感を大切にしたいなとは思っています。あとはさっきも言ったことなんですけど、『skydiving magazine』を媒介にしてアーティストとか企業とコラボレーションをしていきたいんですよね。
平野さん:『skydiving magazine』を出すタイミングで展示会をやるようにしているのも、それと通じるところがあって。やっぱりマガジンだけだと限定的な世界になっちゃうから、もう少し人と関わることで広がってほしいなって。もちろんコラボレーションになると向こうの立場とかもあるから、私たちのやりたいことを100%できなくなるけれど、その制限があるからこそ思いつくアイデアとかもあって。それはそれで良いなって。

一ノ瀬さん:『STUDY』はいろんなクリエイターの内面にあるものをまとめたものだけど、『skydiving magazine』はあくまでも自分たちの中にそれを求めているよね。
長畑さん:一枚のアルバムみたいになってるし、そのときどきの自分のモードがきちんとある。だから、『skydiving magazine』は最近でいちばん悔しいと思った雑誌だったね。ファッション雑誌じゃないんだけど、すごくそれらしいというか。それは既存のものがすごく狭い範囲でファッションを捉えているからなんですけど、それだと自分たちで枠組みをつくった中で遊んでるだけだから面白くないんですよ。
でも、『skydiving magazine』はファッションを可能なかぎり広く捉えたうえで、「これはファッションに成り得るのか?」って問いかけをしつつも、自分たちでその答えを用意している感じもある。だから、すごくファッション的なものになってるなと。モデル選び、色、シチュエーション、写真の撮り方、あと機材の選び方とかもファッション的に選んでる感じがする。これが、なんとなくフィルムで撮った写真が並んでたら面白くなくて。こうやってデジタルでパキっと明確に撮ってるのがうまいなって。
平野さん:それもすごく気にしていて。流行りに乗っかるとか、お洒落にする方法ってなんとなくわかるんですね。記号と記号を組み合わせたりするものだから。でも、そうしちゃうと私たちの個が薄まってしまう気がして。
一ノ瀬さん:いまどき珍しいよね、こういうどこまでも澄み渡るくらいクリアな写真って。最近はフィルムで撮る人が多いからなおさら。
長畑さん:僕としては、写真家の表現したいことにフィルムとデジタルどっちが合うかって話だから、最終的にはどちらでも良いと思っていて。フィルムを使ってる人が突然デジタルに行くこともあるし、その逆の可能性だってあるから。ただ、写真の潮流っていう意味では、デジタルを使う方が面白い表現ができるだろうなとは思うし、そもそも写真表現って技術と常に並走してきたものだから、それがフィルム回帰によってなくなってしまうのは残念だなと思う。なんか写真表現が人間の内側だけの話になっていて、技術のところが置き去りにされている感じがすごくあるから。
それこそ、いまだったらSONYのα7を使うのがいちばん面白いことができるはずなんですよ。でも、最先端のアートを気取ってる人ほど触ってないし、検討すらしていない。その野心のなさはなんなんだろうって思うし、それがクリエイティブをつまらなくしてしまうんじゃないかなって感じるんですよ。

長畑さん:でも、若い子がiPhoneとかで写真を撮ることに抵抗があるのもわかる。日々撮るものだからこそ、何の特別感もないんだろうし。もう写真を撮ってる感覚じゃないんだと思う。
平野さん:私たちは第二世代というか、すでにデジタルがある時代を生きてきたからこそ、フィルムの生っぽさに惹かれるのかもしれないなって。でも、海外のメディアにユルゲン・テラーの記事が載ってたんですけど、最近フィルムで撮ってないですよねってインタビュアーに聞かれたときに「いや、デジタルまじ最高だよ」って言っていて。
一ノ瀬さん:あ、そんなこと言ってんだ。
平野さん:「フィルムに戻る意味がわからない。なんでみんなデジタル使わないの?」みたいなことを語ってたんです。それを読んですごく勇気づけられたというか、この人がそう言ってくれるのかっていう安心感があったんですよ。
長畑さん:それこそ、ユルゲン・テラーが『System Magazine』でストレンジャーシングスのマックス役の女の子(セイディー・シンク)を撮ってるんだけど、半分くらいがiPhoneなんだよね。でも、それがめちゃくちゃ良くて。時代に対する肯定感がすごくあるのよ。
平野さん:ユルゲン・テラーからすると、フィルムで原風景を散々味わって、それから新しいツールが出てきたから「こっちの方がええやん」みたいになったと思うんですよ。その素直さというか、真摯さが良いですよね。

——先ほど『skydiving magazine』がミックステープだというお話がありましたが、『STUDY』はつくり方としては王道感が漂うなと思っています。そのあたりはどう考えていますか?
長畑さん:王道っていう意味で言うと、じつは半分くらいは狙っていて。僕は本屋に卸すときに、インディペンデントのコーナーには絶対に置かないでほしいって頼むんです。『POPEYE』の隣に置いてくれって。それはちゃんとリングに上げてくれっていう意味でもあるんですけど、それくらい本気で僕は『STUDY』をつくっているんです。あと、自分自身がこういうスタイルの雑誌のつくり方に憧れていた部分があったから。そういう意味では他の雑誌と同じですよね。参加している人数が違うだけで。 本当なら、もっとミニマムな感じでつくっていけばよかったのかもしれないんですけれど。
一ノ瀬さん:でも、長畑くんは自分が紹介したいものを紹介したいじゃん。だから、世間一般で言われる雑誌とはちょっと違う気もするけどね。
——ちなみに『STUDY』は刊行回数を増やしていくことを考えたりはしていないのでしょうか?
一ノ瀬さん:これは長畑くんから言うより僕が言うべきかなと思うんですけど、じつは狙ってるんですよ、定期刊行化を。
村田さん:今ってどのくらいのペースで出してるんでしたっけ?
長畑さん:年に1冊は必ずやるようにしていて、それが今度から2冊になります。
村田さん:じゃあ、うまく回ったらもっと出したい感じですか?
長畑さん:想像できるのは年に4回までかな。
一ノ瀬さん:年4回発行してたら立派ですよ。でも、そのために広告を入れるっていう選択を長畑くんはしないでしょ?
長畑さん:それだと持続可能性がないからね。いまって紙媒体に広告を入れたところで向こうにもメリットがそこまでないじゃないですか。その中で関係を築こうと思っても絶対に破綻するから。
死んでも残る、はひとつの価値
——あらためて、いまの時代における紙の価値ってどんなものだと思いますか?
長畑さん:さっきも話に出ましたけど、連続性があるのは重要だなって。人って文脈を失ってしまうと理解がどんどん薄まっていくと思うんですね。あと、写真でも文章でも、それを読む状況はこちらでコントロールできないじゃないですか。Webは、どんな人間にもフィットするような記事を書くことで、それをできるだけ可能にしていると思うんですけれど。紙は買ったときには読む人の気分にそぐわないものでも、何年か置いておくとそぐうものになるかもしれなくて。それって受け手にとっては素晴らしい体験だと思うんです。年月を経てようやく理解できるようになることは、すごく重要じゃないかなって。
村田さん: Webは見る側が向き合わなくて良いですからね。どちらかと言うと覗き見ている感じ。だから、自分が必要ないとか意味がないとか思った情報はすぐにポイってできちゃう。
平野さん:記号的な部分で引っ掛かるものがないとスルーされちゃうよね。

長畑さん:あと紙は効率的なんだよね、やっぱり。長い歴史を生き残ってきた媒体だけある。それをWebが超えるかはこれから先の話になると思うんですけれど。
一ノ瀬さん: WebとかPDFを見せるより全然伝わるしね。長畑くんを紹介するときも本人を紹介するより、『STUDY』を渡した方が理解されやすいし。
——そんなところでしょうか。
長畑さん:こんなことを話してますど、なんか紙が大好きな人みたいには映りたくないわけですよ。なんなら入稿もWebでしてるし。
一ノ瀬さん:うん、俺なんか人一倍インターネット見てるもん。
長畑さん:ただ、メディアの話になるとWebはきちんと機能していないから、やっぱり紙だなと思うわけで。
平野さん:でも、紙についても無駄は減らしたいですよね。明らかにインターネットの情報速度に勝てないのに、同じようなことを雑誌でしていくのは意味がないと思う。
一ノ瀬さん:最近の雑誌はさ、あるページではこう言ってるのに、次のページ開いたら真逆のことを言ってるとかよくあるからね。そうなったらニュースサイトをコピペして、そこに広告を加えて売ってるだけで、もはや雑誌じゃないんだよ。それで最終的には、Instagramで有名な女の子を探して取り上げるっていう。そうなったら本末転倒だよね、紙の独自性を何も活かしてないから。
長畑さん:だから、月刊誌がいちばんダメだよね。情報に追いつけないわ、中身も精査できないわ。それでコンビニに置かれて、立ち読みで何万部も廃棄されちゃう。そんなことやっちゃダメだと思う。こんなエコが叫ばれている時代に。
一ノ瀬さん:月刊誌でも良い雑誌はいっぱいあるんだけどね。俺、『ギターマガジン』とか本当に毎月素晴らしいと思ってるし。
長畑さん:俺も『POPEYE』とかは良い雑誌だと思ってるよ。でも、ああいう雑誌が素晴らしいのは 世の中のトレンドとかを気にせず、自分たちで何に価値があるかを決めて動いてるからなんだよね。
一ノ瀬さん:だから、部数が少ないっていうのもある意味正しいよね。『STUDY』だって何万部刷りたいっていう話じゃないしさ。本当に届けたい人たちに向けて雑誌をつくりたいだけっていう。俺たちが死んでも、神保町で『STUDY』ってなんやねんとか言われながら読まれたいよね。
平野さん:もしかしたら、50年後くらいに誰も発見してなかった文字の間違いとか発見されるかもしれないですよ(笑)。

PROFILE
長畑宏明
編集者。1987年大阪府生まれ。大学在学中に音楽雑誌『クッキーシーン』でライターのキャリアをスタート。また、同時期にスナップ&レビューサイト『howtodancewithyou』を立ち上げる。大学卒業後はウェブ会社に就職。2014年春に独立、同年冬にインディペンデントファッションマガジン『STUDY』を創刊。
PROFILE
一ノ瀬雄太
アートディレクター。1986年生まれ蠍座のA型。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業後、株式会社東京ピストルにて修行。現在はクリエイティブチーム「世界」に所属する。また、ロックバンド「快速東京」のギターでもある。
PROFILE
平野正子
1993年日本生まれ、タイ育ち 。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒 業。フリーランスとしてアートディレクション、写真撮影、グラフィックの制作まで幅広くこなす。
PROFILE
村田実莉
1992 年東京生まれ。2016 年多摩美術大学テキスタイルデザイン学科卒業。テキスタイルデザインのみならずアートディレクション、グラフィックデザイン、スタイリング、空間デザインなど幅広く活動する。
